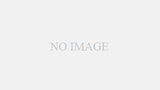以前読んだ記事ですが、桃太郎を知らない子どもが増えているとのこと。
「昔話を知らないといけないの?」と言われると、答えに困りますが、古くから語り継がれていたお話がだんだん子ども達の記憶から去っていくのかと思うと、非常に残念ですね。
何も昔話が良くって、今の絵本が良くないという気はさらさらありません。
どうしても、「ぐりとぐら」などの定番絵本を思い浮かべてしまいますが、若い作家さんの絵本も好きなものはたくさんありますから。
それに、みんながよく知っている「アンパンマン」だって、初めて描かれたのは1973年ですから、今から47年も前なんです。
バーバラ・クーニーなど海外の「古き良き時代の絵本」も好きだけど、現代作家の作品も好き。
なので、「古いから良い」ということではなく、「昔から読みつがれている物語も、大事に次世代につなげて欲しい」というところかな?
まあ、私の周りでは、「桃太郎」や「したきりすずめ」などの昔話を好んで読み聞かせ
されているお母さんとかたくさんいらっしゃるので、統計だけで判断してしまうのも、
あまり良くないことですが・・・
古いものも新しいものも「良いものは評価される」時代でありたいですね。
と書いていたら、最近は「アンパンチが暴力的だからうちはアンパンマンは見せない」というお母さんがいらっしゃるとのこと。
確かに、パンチ自体は暴力と言われても仕方がないですが、そこだけを切り取って「暴力的」というのはちょっと違うのかな?と。
とは言え、子供の教育は、極端に間違ったことでなければ、ある程度その家の方針というものがありますから、「暴力的」と思うのなら、見せないという選択肢もありますよね。
私としては、男の子二人育てた経験から言って、「アンパンマンを好きで観ていたからと言って、特に暴力的になったことは無い」と言い切れますが。
そう言えば、知り合いに、「ドラえもんは、ジャイアンがいじめっ子だから、将来いじめるような子になってはいけないので見せない」というお母さんが居ました。
あと、クレヨンしんちゃんも、「お尻を出したり下品だから」という理由でダメ。
絵本で言えばセンダックの「かいじゅうたちのいるところ」も、「かいじゅうがリアルで怖そうだから」ということで、見せないのだとか。
そうなると、あまりにも親が最初に選別し過ぎて、子供の選ぶ余地が無くなるのでは?と思いましたが・・・
ネットでは、「親がしつけられないから、アンパンマンのせいにしている」という批判も多いのですが、そういうことでは無いんですよね。
何が良い悪いではなく、「子どもがどうしたいのか?」「子どもにとっては、どうするのが良いのか?」を真剣に考えるべきなのでは?と。
聞くところによると、最初に「暴力的」と発信したのは、子育てに疲れたお母さんで、心身ともに疲れている中、子どもがアンパンチを浴びせてくるから、ということらしいです。
だとすれば、暴力的かどうかの議論よりも、そこまで心身ともに疲れ果てた状態で子育てしなければならない、今の子育て事情が、一番問題なのでは?と思います。